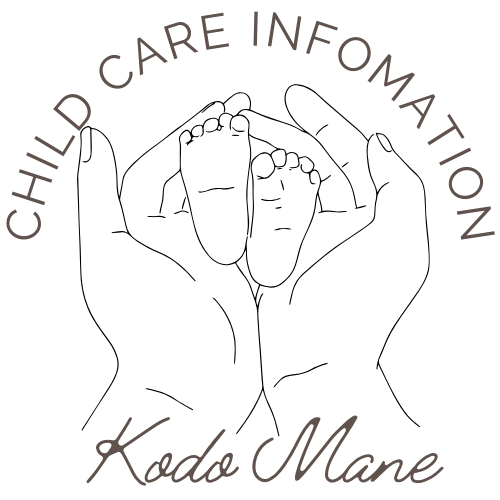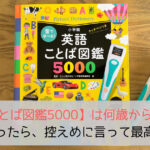おっぱいも飲んだし、オムツも替えたのに、理由が分からない!
泣き止ませられなくて、私ママ失格・・・
そんな風に自分を責めて落ち込んでませんか?
赤ちゃんは生きていくために
「泣く」ことで意思表示をしています。
赤ちゃんが泣くのは、決して悪いことではありません。
まだ泣くことしかできないから、
泣くことで、コミュニケーションを取って
ママにお世話をしてもらうことで、
守ってもらっているんです。
でも、きっとママは泣いている理由が、
分からず焦ったり、イライラしたり、
不安になったり、落ち込んだりすることがありますよね。
そんな時に、泣いている理由と対処法が分かれば、
赤ちゃんをなだめることができ、ママも心休まる時間が増えますよね。
そこで、この記事では赤ちゃんの泣く原因別あやし方と対処法を解説します!
こんな方におすすめ
- はじめて出産したママ
- 赤ちゃんのが泣いていると焦ってしまうママ
- 赤ちゃんが泣いている理由が分からなくて不安になってしまうママ
- 赤ちゃんが泣いているのを一秒でも早くなだめたいママ
赤ちゃんが泣く理由11選と理由別のあやし方と対処法
①お腹が空いている
赤ちゃんが泣く最も多い理由の一つに「お腹がすいた」という理由があります。
そんなのは分かってる!
って思うかもしれないですが、
実は「泣く」サインはお腹がすき過ぎているサインで、
泣き始めた状態から授乳をしようとすると、特に授乳に慣れていなママにとっては難易度が高くなってしまいます。
泣き始めると赤ちゃんは、泣くのに夢中になって、舌が上がりおっぱいを上手くくわえることができません。
あやし方
お腹が空いて泣き始めてしまったら
まず、
赤ちゃんを縦抱きにしてトントンしたり、
ゆらゆら揺れるなどし、なだめてから授乳を始めましょう。

授乳に慣れないうちは、赤ちゃんをなだめるのも大変ですよね。
赤ちゃんも、泣くことで体力を使ってしまいますし、
泣きすぎると疲れて、せっかく吸い始めてもあまり飲んでくれないということにもなってしまいます。
そのため、できるだけ泣き始める前に授乳を始めると良いですよ♪
対処法
泣き始める前の、お腹が空きはじめたサインにはこんなものがあります。
●体がモゾモゾと動き始める
●手や足を握りしめる
●口を開ける
●手を口や服の袖に持っていき、チュパチュパする
●「クー」、「ハー」といった柔らかい声を出す
●舌を出す
●背伸びをするなど、動きが大きくなる
このようなサインがあったら、
授乳の準備を始めてあげましょう。
基本的に赤ちゃんが欲しがるときに欲しがるだけあげて大丈夫なので、
母乳でもミルクでも3時間より早く欲しがってもあげてくださいね。
② おむつが濡れている
むつが汚れていると、赤ちゃんは不快に感じて泣きます。
おしっこを1回しただけであれば、おむつの交換をしなくても大丈夫ですが、
おむつがずっしりと重くなるくらい膨らんでいたり、
うんちの臭いがするときは交換してあげましょう。
対処法
おむつかぶれを予防するために、おまたやお尻に「ワセリン」や「プロペト」を塗ってあげてもよいでしょう。
皮膚に直接おしっこやうんちが付かないので、
刺激が少なく赤ちゃんのデリケートなお肌を守ることができますよ。
③ 眠い
自分で上手に眠ることができないから、眠くても泣くよ。
対処法
●耳を引っ張る
●おもちゃに興味がなくなる
●ボーっとする
●視線が合わなくなる
●背中をそらせる
●顔をこすりつける
●転んだり、物にぶつかる
●あくび
●ぐずる
●ハイテンション(奇声を発する、急に不機嫌になる)
●手足がポカポカ
※あくび・ぐずる・目をこするようなら眠すぎるサイン!
こんなサインが出てきたら、眠いサインだから寝かせる準備をしてあげましょう。
あやし方
まんまる抱っこでトントンしたり、
ゆらゆらしたり、
おくるみで包んだり、
抱っこ紐で寝かせたり、
はじめは赤ちゃんが寝られるなら寝かしつけの方法は何でもOKです!
④ 疲れている
一日に何度も寝る赤ちゃん。
ですが、お昼寝が上手にできなかったり、
寝るタイミングを逃してしまったりすると、疲れがたまってきます。
また夕方になると、赤ちゃんも一日の疲れから泣きやすくなります。
あやし方
そんな時は、光や音など刺激になるものをなくして、薄暗く静かな部屋でゆっくり過ごさせてあげましょう。
赤ちゃんはママのお腹の中いたときの音を聞くと、
とっても安心して落ち着きやすかっり、
音があることで眠りを中断されにくくなります。
そのときに、効果的な音が
ホワイトノイズ・ピンクノイズ・ブラウンノイズ
です。
ノイズを使用するときは、赤ちゃんから2mほど離して、
音量は50dB程度にしましょう。
(50dBとは、小さな声で話したり、静かな事務所にいる時の音の大きさです。※普通の声で話している時の音量は60dBぐらい。)
その他にも、
マッサージをしてあげるなどスキンシップを増やしてあげると赤ちゃんも癒されて、
泣き止んでくれることもありますよ。
対処法
昼寝がしっかりと取れず、疲れすぎてしまうと、
夜間の夜泣きにもつながるので、
赤ちゃんの「眠いサイン」をよく観察することや、
各月齢の活動時間を意識して、寝かしつけの参考にしてくださいね。
| 月齢 | 活動時間の目安 |
| 0~1か月 | 40分 |
| 1~2か月 | 40分~1時間 |
| 2~3か月 | 1時間~1時間20分 |
| 4~5か月 | 1時間20分~1時間30分 |
| 6~8か月 | 2時間~2時間30分 |
| 9か月 | 2時間30分~3時間 |
| 10か月~1歳2か月 | 3時間30分~4時間 |
⑤ 暑い・寒い
赤ちゃんは大人よりも体温調節が苦手です。
室温が低すぎたり高すぎたりすると、寒さや暑さで泣いてしまうことがあります。
対処法
赤ちゃんの肌に触れてみて、背中に汗をかいていたり、手や足先が温かく、汗ばんでいるよなら暑いサインです。
逆に、太ももやお腹が冷たかったり、
手先や足先が紫色の場合は寒いサインの可能性があります。
室温を調整したり、適切な服装をさせてあげましょう。

もし、室温や衣服を調節した後も、
体温が38℃以上の場合は、発熱しているので、病院を受診することも検討してくださいね。
特に生後3か月未満の赤ちゃんの発熱は緊急性が高いので、夜間や休日でも早めに受診をするようにしましょう!
⑥ 不快感
うんちが出てなくてお腹が張っていたり、げっぷが出なくて気持ち悪いといった不快感があるときも、
赤ちゃんは泣いて訴えます。
対処法
お腹のが張っていて苦しそうなときは、マッサージや綿棒浣腸をしてお腹に溜まったガスを出してあげましょう。
おっぱいやミルク、オムツでもない場合は、
一度縦抱きにしてトントンとやさしく背中をたたいてあげたり、
ゆらゆら揺れてみましょう。
するとげっぷが出て、すっきりした赤ちゃんは泣きやむことがあります。
抱っこの向きで泣くこともあるから、横抱き、縦抱き、おんぶ、縦揺れ、横揺れなど色々試してみるのもアリです!
⑦ 痛い

いつもの泣き方とどこか違う!
おっぱいやミルク、オムツでも抱っこでもなく泣き続けている場合は、
どこかケガをして痛がっていないか、オムツかぶれをして痛がっていないか、
ケガや湿疹などの有無を確認しましょう!
「ヘアーターニケット症候群」といって、髪の毛や糸が指先に巻き付いてしまって、
強く巻き付くと痛みや腫れが生じます。
ひどくなると、血流が止まり指先が壊死することにもつながってしまいます。
何をしても泣き止まないときはくまなく全身をチェックしてあげましょう!
髪の毛や糸くずが絡みついていたら、ピンセットや小さなはさみで取ったり、切ったりしてあげましょう。
自分では取れない場合や、取れたとしても早めに病院を受診しましょう。
⑧ さみしい
ママにだっこして欲しい、優しく声をかけて欲しいって、赤ちゃんは甘えてなきます。
あやし方
優しく抱っこして、優しく声をかけてあげましょう。
子守歌などを歌ってあげても良いですよ。
⑨ 暇
寝ていることに飽きちゃったって泣くことも。
大人もずっと同じ姿勢で、何も見えない状態でいるのは退屈ですよね。
生まれたばかりの赤ちゃんでも30㎝先までは見えますし、
音も良く聞こえます。
あやし方
ベビージムで遊んだり、月齢に合わせたおもちゃで一緒に遊んだり、
ママがお歌を歌ってあげるなど刺激を与えてあげると良いですよ。
赤ちゃんの月齢別オススメおもちゃ
⑩ 場所・人見知り
生後6か月頃になると「ママ」と「他人」を区別できるようになってくるため、
人見知りをすることがあります。
また、知らない場所に行くと不安を感じて泣くことがあります。
あやし方
人見知りや場所見知りも、
赤ちゃんが成長している証です。
ママとしっかり愛着形成がされているという証拠でもあります。
まずは優しく声をかけ、抱っこして安心させてあげよう。
ママにくっつき、その場所が安全な人・場所だと分かると、
少しずつ慣れていきますよ。
⑪ ぐずり期
赤ちゃんには、「黄昏泣き」、「メンタルリープ」といった脳が急激に成長・発達する時期があります。
この時期はぐずりやすく、何をしても泣き止んでくれなくて、ママもしんどくなってしまうことも。
対処法
まずは、ぐずる時期があること、
この時期には赤ちゃんは成長しているんだって知ることから始めましょう!
黄昏泣き(コリック)の原因と対処法
生後3週目頃に始まる、夕方に長時間泣き続ける症状です。
生後6か月頃にはおさまるといわれています。
☑1日に3時間かそれ以上赤ちゃんが泣く
☑1週間に3日かそれ以上激しく大声で泣き続ける
この状態のときは黄昏泣きをしていると考えられます。
黄昏泣きは現在の所はっきりとした原因がわかっていません。
ですが、アメリカ小児学会は「黄昏泣きを起こす理由」を発表しています。
参考
◇赤ちゃんの消化器官が未発達のため、不快な症状が発生していて泣いている
◇胃酸が逆流して泣いている
◇お腹にガスが溜まっている
◇新しい刺激が多く敏感になっている
◇一日の疲れが出てきて泣いる
◇母乳やミルクに含まれる成分による食物アレルギー
◇タバコの煙
こういった理由で泣いていることが考えられるので、
夕方から何をしても泣き続けている場合は、
次の対処法を試してください。
◆ ミルクを飲ませすぎない
生後3か月未満の赤ちゃんは特に、満腹中枢が未熟なため、
ミルクを与えると必要以上に飲みすぎてしまうことがあります。
ミルクの飲みすぎで不快症状が起きている可能性があります。
基本的には欲しがるときに欲しがるだけの授乳で良いですが、
本当にお腹が空いているのかは、「おなかの空いているサイン」を見て
授乳をするようにしてください。
1日当たり50g以上体重増加がみられる場合は、飲ませすぎのサインになりますので、
気を付けてくださいね。
◆粉ミルクの場合、加水分解乳に変更
ミルクの成分にアレルギー反応を起こしている場合もあります。
その場合は、「低アレルゲンミルク」に変更した方が良いか小児科医に相談してみましょう。
食物過敏性が不快感を引き起こしている場合は、ミルクを変更すると数日で黄昏泣きが減少することがありますよ。
◆抱っこ紐を使う
赤ちゃんはママとぴったり密着するととても安心し泣き止むことが多いです。
こういった、新生児から利用できる抱っこ紐を使ってあげると、
ママの手や腕の負担も減らせますよ。
◆ ホワイトノイズを使う
◆ おしゃぶりを与える
哺乳が確立していない新生児のうちにおしゃぶりを使うと、母乳拒否を起こしやすくなってしまいます。
しかし、「寝かしつけのときだけ」など限定しておしゃぶりを使うことで、
赤ちゃんの入眠をスムーズにしてくれる場合があります。
◆ 赤ちゃんをママの胸の上に置き、うつ伏せにする

うつぶせ寝にすると赤ちゃんが落ち着くことがあります。
お部屋の中なら、ママも赤ちゃんも肌をだして、
肌と肌をくっつけてあげるとより効果的です♡
◆スワドルやおくるみで包む
スワドルやおくるみで赤ちゃんを巻いてあげると、落ち着くことがあります。
生後4か月未満の寝返りをするまでは、寝るときにスワドルやおくるみを使ってあげると、
赤ちゃんがぐっすり寝てくれますよ。
◆小児科医に相談する
もし、これまで書いた対策をしても激しく泣き続けてしまう場合は、
病気がないかを診断してしもらうため小児科医に相談してみましょう。
メンタルリープの原因と対処法
メンタルリープは、赤ちゃんの脳が急激に成長することで、
知覚や思考パターンが新しく構築され、物事の捉え方が変化するので、
赤ちゃん自身戸惑いや不安、不快感を覚えてぐずりやすくなったり、夜泣きが増える時期です。
出産予定日から数えて、生後20か月までに、10回このリープが訪れるといわれています。
まずは、ママやパパがメンタルリープを知り、理解することが大切です。
そして、不安定な時期の赤ちゃんを温かく見守り、サポートしてあげることが大切になります。
メンタルリープの時期
◇生後5週目頃:「五感のリープ」で赤ちゃんの世界が広がる
◇生後8週目頃:「パターンのリープ」で規則性を学ぶ時期
◇生後12週目頃:「推移のリープ」で物事の流れを理解するステップ
◇生後19週目頃:「出来事のリープ」で動きや現象に興味を持つ
◇生後26週目頃:「関係のリープ」で人や物との距離感を学ぶ
◇生後37週目頃:「分類のリープ」でものをカテゴリー分けして考える
◇生後46週目頃:「順序のリープ」で行動の手順を覚える
◇生後55週目頃:「工程のリープ」で物事を段階的に進める力を育てる
◇生後64週目頃:「原則のリープ」でルールや法則性を試す
◇生後75週目頃:「体系のリープ」で社会のしくみを学び始める
これらの時期はあくまで目安であり、個人差があります。
メンタルリープの時期はサイトやアプリで簡単に検索することができます。
\\あなたの赤ちゃんのメンタルリープはいつ?//
メンタルリープ計算できるサイトはこちら
メンタルリープの時期は、残念ながらこれでおさまるっていう解決方法はありません。
ですが、赤ちゃんを安心させてあげることで落ち着きやすくなります。
抱っこしたり、マッサージしたりとスキンシップを図る時間を増やしてあげましょう。
そして優しく声をかけてあげなだめてあげてくださいね。
他にも、赤ちゃんは「いつも通り」が安心します。
起床時間や就寝時間をそろえて生活リズムを整えてあげましょう。
寝る前のルーティンを続けてあげることでも安心できますよ。
メンタルリープは子どもにとって成長の一環であり、時期が過ぎると落ち着いてきます。
ママやパパなど周りの大人が理解を深め、適切にサポートをしてあげましょう。
まとめ
赤ちゃんが泣くのは、自分の気持ちを伝える唯一の方法です。
赤ちゃんの泣き声は、単なる泣き声ではなく、大切なメッセージです。
そうだと分かっていても、
赤ちゃんが泣き止んでくれなくて、不安になったり、イライラしたり、自分を責めてしまうときは、
赤ちゃんを安全な場所に寝かせて、
一旦、赤ちゃんと離れて、自分の気持ちも落ち着かせてみてくださいね。
もし、その場にパパや他の人がいるなら代わってもらって、
一人で頑張りすぎないことです。
誰かを頼ることは、赤ちゃんを元気に育てていくために必要なことです。
産後ケアを利用したり、
産後ヘルパーさんに頼ってみるという方法もあります。
誰一人として、たった一人で育児できる人はいないから、
頼ることを遠慮しないでくださいね。